
 116
116

 116
116
タイトルの「信濃の国」とは、とある歌の題名なのだが、これはおいおい説明するとして、「信州(県)」に改名しよう、などと言って話題になっている「長野県」は、不思議な県である。住んだことは無いのだが、一時期、本籍が長野になったことがあり、全く無縁の土地でもないので少し長野県について考えてみた。
長野県は、大部分が山間部であることも原因のひとつだと思うが、その広い県域のため、全く異なる地方が合体している雰囲気がある。まあ、どの県も、元はと言えば別々の藩(県)が合体して完成しているから、例えば「愛知県」などでも、「尾張(名古屋)」と「三河(豊橋、岡崎等)」とは、まったく雰囲気、文化圏が違う。「京都」と言ってもけっして全部が盆地ではなく、海岸線もあれば港もある(信じられない人もいるようだが、日本海に面している)。青森県と言っても、日本海もあれば太平洋もある。岐阜県と言っても、山間部もあれば堆積平野もある。たった一つのイメージで語られる県の方が少ないのは確かだ。しかし、長野県の場合は、その領域の境界が、日本を代表する山脈だったりするので、全く違う地域の合体という雰囲気は、他県を圧倒する。
長野県は、大きく4つに分けて考えられており、さらに細かく分類するならば、7つのエリアに分けられる(県庁のページをみたら10に分けられていた)。例えば、スキーをする人にとっては判りやすいと思うが、長野市を中心とする「北信」エリアは、志賀高原、野沢温泉など、どちらかと言うと「越」の色が濃い領域である。「東信」エリアは、軽井沢というリゾート地を抱え、比較的広大な平地(台地、高原)を持つ。「南信」は、諏訪湖を中心とする「諏訪エリア」と南アルプスのふもとの「伊那エリア」から成る。伊那は「愛知(三河)」との繋がりが濃くなっており、比較的温暖※な印象がある。「中信」とされるのは、松本を中心とする領域であるが、これは北アルプスから木曽までを含む。サンアルピナ、八方尾根などの一大スキーエリアを抱える豪雪地帯から、松本、塩尻というちょっとした都市部を経由し、南は木曽を経て岐阜県に至る領域である。途中、例に挙げたスキー場で見ても、「志賀高原・野沢温泉」から、「軽井沢」、「蓼科・富士見高原」、「八方尾根・青木湖」、「御岳国際・乗鞍」と、これが果たして同じ県なのか、と驚かされるバラエティに飛んだ県である。無論、各所に出張所、支所があるのだろうが、もし、長野市にしか県の機関が無かったら大変なことになる。例えば運転免許試験場など。
こんな県だから、端の方に住む人にとっては、「ま、一応長野県だけどさ」という表現になってしまうのも仕方が無い。軽井沢付近に住む知り合いは、「長野」ナンバーの車を恥ずかしいと言い、飯田に住む知り合い一家は、皆、名古屋に買い物に行く。木曽のとある地域は、今後、岐阜県に合併するようだし、八方あたりでは、日本海の魚が大量に入荷してくる。
もう、県民の意識がばらばらである。そうなると、何かを使って統一の意識が必要となってくる。それが「信濃の国」である(らしい)。ウソかホントか知らないが、県民が誰でも知っている歌らしく、県議会で分県の議決がされそうになったとき、議場の周囲で分県反対の人々が信濃の国を歌って、ひっくり返ったとか。
この「信濃の歌」は、長野県の公式ページで聞けるそうだが、内容を簡単にまとめると、登場する素材が、各地の物がきれいに分散しているのだそうだ。「佐久平・善光寺平・松本平・伊那谷」「浅間山・乗鞍岳・御嶽・駒ヶ岳」「千曲川・犀川・木曽川・天竜川」、地形、山、川、いずれを取ってもきれいに分散している。作者の苦労の後が読み取れる。
しかし、それにしても「信濃の国」であって「長野県民の歌」でないところが悲しい。「長野」と命名すると、各地で反対運動が起きるのだとか。特に「長野」と「松本」の敵対心は強く(一応、ライバル心と言っておこうか)、県の成立直後から、何かの施設ができると対する別なものを誘致する、という合戦が続いたそうだ。中でも日本銀行の支店は、いまだに松本市にしかなく、県庁所在地に無いのは珍しい。
また、県を代表するような公的機関、私的企業いずれも、「長野」を名乗らないのも長野県ならではの特徴である。県を代表する国立大学が「信州大学」だったり、県内最初の放送局が「信越放送」だったり、新聞社が「信濃毎日新聞」だったり。
どうも「長野」という言葉は「長野市」あるいは「長野市を中心とする北信地域」を指すことが強調されるらしく、全体としては無難な「信」の字が使われるようであるが、さて、それでは「長野」とはどこから発生したのかと言うと、1870(明治3)年9月,伊那県の管轄する地域のうち,
佐久・小県(ちいさがた)・更級(さらしな) ・埴科(はにしな)・高井・水内(みのち)の各郡に属する地域が
分離されて,現在の中野市の旧代官所に設置された中野県の管轄となったのが始まりで、最初はにごらず「なかの」だったらしい。それが、農民一揆の焼き討ちに合い、1871(明治4)年6月に善光寺宿を中心とする長野町に移転し、「ながの県」が発足したという。
それでは、その頃「松本」はどうだったかと言うと、中信(安曇・筑摩[木曽を含む]2郡)と南信(諏訪・伊那2郡)、
さらに飛騨国の全域3郡をあわせた 筑摩(ちくま)県の中心であったのだが、県庁の出火により1876(明治9)年8月21日に廃止され、飛騨が岐阜県に、残りが長野県に編入されることとなり筑摩県は消滅している。このとき、地理的中心でない長野の方に編入となったのは、政府の方針に忠実でない住民への懲罰である,などともよく言われているそうだ。そんなこともあり、松本と長野の対立は、明治から現在にまで至るようだ。
とにかくここで、長野県の統一が行われたのだが、やはり広い県域、文化圏・生活圏の違いから、研究者の間でも「信州合衆(州)国」と呼ばれている、とのことで、あながち素人の筆者の判断も間違ってはいないようだ。
こうした長野県民にとって必要だったのが、多民族国家アメリカ合衆国の「星条旗・国歌」のような、「県旗と県歌「信濃の国」」なのかもしれない。
最後に、こんな多民族県である長野県の変遷を示す。(参考:長野県のページ議会の沿革)
■幕末当時:14藩、幕府直轄地、旗本領
■明治元年(1868):伊那県置県
■明治3年(1870):伊那県官下北部6郡→中野県 高須藩→名古屋藩
■明治4年(1871):竜岡藩→中野県、中野県→長野県
廃藩置県により、各藩は県として発足 14県
■明治5年(1872):北部8県が長野県 南部6県と飛騨が筑摩県に統合
■明治9年(1876):筑摩県庁が消失により合県、現在の長野県
| 旧国名 | 明治維新 | - | 版籍奉還直後
1869.7.1 |
- | 廃藩置県
1871.7.14 |
第1次
府県統合 1871.11 |
|
| 信濃国 | 岩村田藩 | → | 岩村田県 | 長野県
71.11.20 |
長野県
76. 8.21 |
||
| 小諸藩 | → | 小諸県 | |||||
| 上田藩 | → | 上田県 | |||||
| 松代藩 | → | 松代県 | |||||
| 須坂藩 | → | 須坂県 | |||||
| 飯山藩 | → | 飯山県 | |||||
| - | 中野県
70.9.17 新設 |
長野県 |
|||||
| 竜岡藩 | 71. 6. 2
廃藩 |
||||||
| 伊那県
旧三河県を
|
筑摩県
71.11.20 |
||||||
| 伊那県
68.8.2 |
69. 6.24
伊那県 |
伊那県 | 伊那県 | ||||
| (三河国) | 三河県
68. 6. 9 |
額田県
71.11.15 |
愛知県
72.11.27 |
||||
| 信濃国 | 高島藩 | → | 高島県 | 筑摩県
71.11.20 |
長野県
76. 8.21 |
||
| 高遠藩 | → | 高遠県 | |||||
| 飯田藩 | → | 飯田県 | |||||
| 松本藩 | → | 松本県 | |||||
| (飛騨国) | 飛騨県
68. 5.23 |
高山県
68. 6. 2 |
高山県 | → | 高山県 | 岐阜県
76. 8.21 |
|
長野県成立後の変遷・事件
| ■議事堂 | |
| 明治20年(1887)6月 | 着工 12月21日落成式 |
| 翌日焼失 | |
| 明治22年(1889)10月 | 竣工 |
| 大正2年(1913)5月24日 | 再び焼失 |
| 大正3年(1914)10月19日 | 落成 |
| 昭和43年5月 | 現議事堂落成、今日に至る |
| (なんだかな〜 燃えてばっかりいるのね) | |
| ■移庁論・分県論 | |
| 明治9年6月19日 | 筑摩県庁の火災焼失により長野県発足、県庁が北に偏在していることから移庁論の論拠となる。 |
| 明治13年(1880) | 第2回通常会にて県庁を県の中央に移すべきとの建議書が提出、反対派議員の欠席により流会。 |
| 明治23年(1890) | 提出された移庁建議書により第13回通常会は大騒動となる。
移庁賛成に回った反対派議員の宿舎が襲われ暴行、入院。 賛成派は上田に移り、県会の上田開催を要求。 反対派は入院中の議員を担ぎこみ県会の開会を強行。 |
| 明治24年(1891) | 松本町、島立村の納税拒否問題、松本警察署、東筑摩郡長邸の破壊事件 |
| 明治41年(1908)5月 | 県庁舎焼失を機に松本への移庁論再燃 |
| 大正15年(1926) | 郡役所廃止にともなう移庁運動 |
| 昭和8年(1933)4月 | 臨時県会にて移庁意見書案が提出賛成派議員が上回るが、傍聴者と警戒の警察官との騒然としたなかでの議論となり時間切れ閉会。 |
| 昭和23年(1948) | 県庁舎の一部焼失を機に分県論、予算案の議論が宙に浮き議場内であわや乱闘。反対派議員の牛歩戦術により議事引き延ばしにて大混乱。このとき「信濃の国」事件発生、流会。翌日、分県に関する意見書を提案しようとするが、反対派市民が賛成派議員の登院を阻止。
その後、賛成29票、反対26票、白紙3票となるが、法定得票数の30票に達せず。 |
| 昭和37年(1962) | 県庁の新築問題を機に再度移庁論が再燃。もう、いいかげんにしろや。
このとき、政府が「新産業都市を指定」という政策を打ち出し、松本・諏訪地区が指定されたことなどから、移庁論の決議初は提案されず。 |
| 昭和39年(1964)2月 | 定例会において「県行政の普遍均等化のために行うべき施策については、その実施について一応の方向づけがなされた」と報告。 |
| 現在に至る。 |
いかに長野と松本が仲が悪いかがわかる史実である。
比較的温暖※
公開直後に、読者の方からの指摘があり、「伊那エリアは温暖ではない」とのことであった。伊那地方には何度も行ったことがあるのだが、住んだことは無いので、少ない経験からの勝手な思い込みかもしれない。
こういう場合には、即座に調査するのが私の特徴でもある。早速気象台のデータベースから資料を取り寄せてみた。長野県内の気象台のある4箇所、飯田、諏訪、松本、軽井沢、長野の5箇所の1971年から2000年までの月平均のデータと、比較用に静岡のデータを入手しグラフに描いてみた。
確かに、飯田は年間を通して月平均がマイナス気温にならないという長野県の中では、「比較的気温が高い」地域ではあるが、決して「温暖」と言えるほど高くはない。いわゆる「温暖な地域」の例として静岡のデータを並べて表示してみたのだが、下のグラフで示されるように、かなり温度差がある。軽井沢は極端に低い値であるが、それ以外は、意外にも大差無く、飯田以外は1月2月が氷点下になるところぐらいしか違いが無い。
やはり長野県は寒い地域であった。
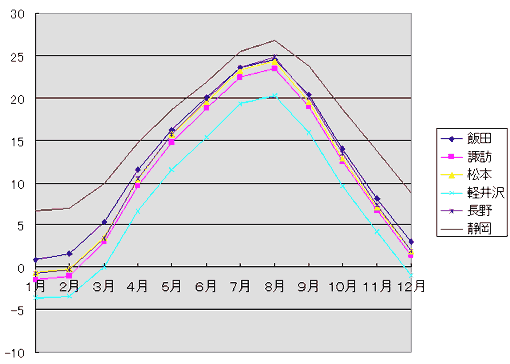
それでは、何故、「比較的温暖」などという気がしたかというと、私が訪れたとき、決まって晴天で、一度も雨にも雪にも降られたことが無かったのである。それじゃ晴天率が高いのか、と思って調べたのだが、これも誤り。
| 日照時間
(時間) |
降水量
(mm) |
積雪最大
(cm) |
|
| 飯田 |
1985.2
|
1606.7
|
17
|
| 諏訪 |
2101.4
|
1307.0
|
20
|
| 松本 |
2095.7
|
1018.5
|
25
|
| 軽井沢 |
1885.7
|
1197.6
|
32
|
| 長野 |
1901.7
|
901.2
|
30
|
日照時間が最も長いのは諏訪だし、降水量が最も少ないのは長野、積雪が少ないのは飯田だが、これもほんのわずかの差であった。
その他にも、別な方から面白い話を教えて頂いた。
長野新幹線ができて長野周りで東京に出る人が増えたので、あずさを高速にして2時間で新宿に行けるようにしろ、という運動が松本・塩尻地区では盛んなのだそうだ。