
 122
122

 122
122
平成の大合併における岐阜県の変貌は著しい。変化の激しい県は、広島県と岐阜県であろう。その岐阜県では、本日、新たに二つの市が誕生した。
岐阜県は、日本のほぼ中央部にあり、山間部と堆積平野部を持つ。ほぼ中央というのは、地理的にほぼ中央付近にあるのももちろんだが、人口重心となる場所も岐阜県内の「郡上郡美並村」にあるらしい。まあ、この手の話は、政府発表の多少胡散臭い情報であり、いろいろな人が反論しているのだが、中でも興味のある話としては、人口分布情報が、メッシュデータがあるにも関わらず、市町村の役所(役場)の場所で代用していたとか、地球を平面で考えているとか。そこで、あえて球面を台形近似し、正しいメッシュデータで計算しなおした結果、現在の人口重心より、5.5kmほど北にずれた「美並村白山付近
美並ICから東に2.8Km」だったとか。この誤差が統計の20年分の誤差にあたるとか。
まあ、細かい話は置いておくとしても、岐阜県とは、人口分布から見ても、ほぼ真ん中にあることに違いはない。
さて、山間部と平野部を持つ、と書いたが、これもいろいろ反論があるだろう。実際に18年間も住んでいた身からすると、たった二つに分けるのには無理があると思う。平野部だけを例に取っても、巨大な川が3本も流れているせいか、まったく違う文化圏のような雰囲気がある。細かい話を除けば、一般的には「美濃(平野部)」と「飛騨(山間部)」の二つから成る、と言われているのだが、飛騨国は、一旦、今の長野県に属していた歴史もあり、なぜかその後、岐阜にくっついたため、全く異なるものが合併した雰囲気も仕方がない。
こんな岐阜県だが、いわゆる「平成の大合併」以前には、99個もの市町村があった。100を越えているのは、北海道と新潟、長野だけなので、日本で4番目に市町村数が多い県であったことになる。そのせいか、今回の号令により、最も多くの合併劇が進められているのだろうか。
まずは、99市町村の内訳であるが、14市、55町、30村 という状態であった(2000年10月1日時点)。この比率がどの程度のものなのかと、町数÷市数、村数÷市数、という数値を算出し、全国平均と比べてみた。すると、岐阜県が、町数÷市数=3.93、村数÷市数=2.14 という数値に対して、全県の平均は、町数÷市数=3.73、村数÷市数=1.03 となった。
町と市の比率は平均的だが、村の比率が高いことが判る。この比率を越える県は、長野県(3.94)、青森県(3.13)、山梨県(2.86)、福島県(2.80)、沖縄県(2.70)、群馬県(2.36)、だけで、岐阜県は第7位である。これらの県名を見ても、沖縄を除いて、ほとんどが山間部の多い県である。
全国的に見ても「村」の多い県であることが判ったが、絶対数としてはどうなのだろうか。村数の多い順に並べてみると、トップは意外にも、長野県(67)、第二位が、新潟県(35)、であり岐阜県(30)は堂々の第三位である。
市と村の比率を、全国平均の1.0ぐらいになるように村の数を減らすと、16個の村が消えるから、市町村数の合計は83となり、13位まで下がる。平均よりは多いが、現状に比べればましである。
さて、それでは現実の岐阜県は、どういう合併劇を演じたのであろうか。
2003年4月1日に、山県郡の高富町、伊自良村、美山町が合併し、山県市へ
2003年5月1日に、本巣郡の穂積町、巣南町が合併し、瑞穂市へ
昨年の1年間に、4つの町、1つの村が消滅し、2つの市が誕生している。これだけで既に、先ほどの市町村の内訳は、16市、51町、29村 となり、合計96となった。
今後の予定が激しい。
まずは本日、
2004年2月1日に、吉城郡の 古川町・ 河合村・ 宮川村・
神岡町が合併し、飛騨市へ
2004年2月1日に、本巣郡の 本巣町・ 真正町・ 糸貫町・
梶尾村が合併し、本巣市へ
既に確定しているもの(官報公示のあったもの)だけでも、
2004年3月1日に、郡上郡の 八幡町・ 大和町・ 白鳥町・
高鷲村・ 美並町・明宝村・ 和良村が合併し、郡上市へ、
2004年3月1日に、益田郡の 荻原町・ 小坂町・ 下呂町・
金山町・ 馬瀬村が合併し、下呂市へ
検討中を除いて、決定したものだけで、13町、7村が消滅し、4市が誕生する。すると、20市、38町、22村 となってしまう。
さきほどの計算に当てはめると、町数÷市数=1.90、村数÷市数=1.10 となる。これは平均どころか、市の比率の高い方のベスト10入りである。村の比率は、ほぼ平均的といったところか。
ここまでで、一旦、市町村数のランキングをまとめてみよう。当然のことながら、岐阜県が市町村数を減らす間に、他の県も合併を繰り返している。
| 順位 | 2000/10/01 | 2003/02/01 | 2003/12/31 | 2004/02/29 | 2004/03/31 |
| 1 | 北海道(212) | 北海道(212) | 北海道(212) | 北海道(212) | 北海道(212) |
| 2 | 長野県(120) | 長野県(120) | 長野県(118) | 長野県(118) | 長野県(118) |
| 3 | 新潟県(112) | 新潟県(111) | 新潟県(110) | 新潟県(110) | 新潟県(101) |
| 4 | 岐阜県(99) | 岐阜県(99) | 岐阜県(96) | 福岡県(96) | 福岡県(96) |
| 5 | 福岡県(97) | 福岡県(97) | 福岡県(96) | 鹿児島県(96) | 鹿児島県(96) |
| 6 | 鹿児島県(96) | 鹿児島県(96) | 鹿児島県(96) | 岐阜県(90) | 埼玉県(90) |
| 7 | 熊本県(94) | 熊本県(94) | 熊本県(90) | 熊本県(90) | 福島県(90) |
| 8 | 埼玉県(92) | 埼玉県(90) | 埼玉県(90) | 埼玉県(90) | 兵庫県(88) |
| 9 | 福島県(90) | 福島県(90) | 福島県(90) | 福島県(90) | 熊本県(87) |
| 10 | 愛知県(88) | 愛知県(88) | 兵庫県(88) | 兵庫県(88) | 愛知県(87) |
ちょっと市の乱発が気になるところだが、今後も続々と計画されている。協議会によりほぼ日程が決まっているが、まだ今のところ正式発表の無いものとしては、
2004年10月1日目標で、海津郡の 海津町、平田町、南濃町が合併し、ひらなみ市へ
2004年10月目標で、恵那郡の 坂下町、川上村、加子母村、付知町、福岡町、蛭川村が中津川市へ
2004年10月目標で、恵那郡の 岩村町、山岡町、明智町、串原村、上矢作町が恵那市へ
2004年11月11日目標で、羽島郡の 川島町が各務原市へ
以上で、11町、4村が消滅し、1市誕生する。従って、21市、27町、18村
とうとう町の数が半分になってしまった。
| 順位 | 2004/03/31 | 2004/12/31 |
| 1 | 北海道(212) | 北海道(208) |
| 2 | 長野県(118) | 長野県(116) |
| 3 | 新潟県(101) | 福岡県(96) |
| 4 | 福岡県(96) | 新潟県(92) |
| 5 | 鹿児島県(96) | 埼玉県(90) |
| 6 | 埼玉県(90) | 愛知県(87) |
| 7 | 福島県(90) | 福島県(86) |
| 8 | 兵庫県(88) | 熊本県(86) |
| 9 | 熊本県(87) | 鹿児島県(84) |
| 10 | 愛知県(87) | 兵庫県(80) |
相変わらず、登場する県はほぼ一緒であるが、大きく順位が変動した。努力した新潟、鹿児島、兵庫はランクを下げたが、さぼっている福岡、埼玉、熊本は順位を上げている。徐々に、大都市を抱える県が上位にランクし始めたのが面白い。鹿児島か兵庫か、どちらが脱出するのが早いか。そして、代わりにランクインする県はどこか。
わが岐阜県は19位まで後退している。
かなり先の来年の予定(合併特令の期限が2005年3月)まで入れると、
2005年2月1日に、2町7村が高山市に合併
2005年2月1日に、1町3村が関市に合併
2005年2月1日に、2町が可児市に合併
2005年3月31日に、1市4町が岐阜市に合併
2005年3月31日に、6町1村が美濃加茂市に合併
2005年3月中に、9町が大垣市に合併
2005年3月中に、2町5村が1市へ
このあたりの情報は、かなり怪しい情報であるが、とりあえず検討中というものも含め、22町、16村、1市が消滅し、1市誕生となる。従って、21市、5町、2村 となる。
ほとんどが市域となってしまう。合計99市町村から、合計28市町村ということで三分の一以下となり、政府の努力目標を軽く越えている優秀な県ということになる。(念の為言っておくが、私は必ずしも由緒ある地名が消える合併を好ましく思っているわけではない。ただ、政府の言いなりになるということで「優秀」と皮肉っているだけである)
しっかし、無理があるんじゃないかい?いきなり2年半で三分の一って・・・
当たり前の話であるが、上の話は面積を考慮していない。1万平方キロを越える岐阜県と1800平方キロの香川県と、市町村の数で同列に比較するのは間違っている。そんなことは承知で遊んでいるだけである。そこで、少しまじめに面積を考慮して考えてみよう。
再び、総務省の統計局からデータを入手する。しかし、各県の面積というのは、実はいい加減であり、境界が未定の領域が多々ある。日本全土の合計で境界未定地域は
11,019平方キロにも及ぶが、この数値は含んでいない。突然だが、岐阜県の面積が
10,209平方キロであるから、岐阜県よりも大きな面積が見境界地域ということになる。
さて、とにかくこのデータを基にして計算してみよう。同様にランキングを調べる。
各都道府県の面積を、市町村の数で割った数である。
| 順位 | 2000/10/01 | 2003/02/01 | 2003/12/31 | 2004/02/29 | 2004/03/31 | 2004/12/31 |
| 1 | 北海道(394) | 北海道(394) | 北海道(393) | 北海道(394) | 北海道(394) | 北海道(401) |
| 2 | 岩手県(259) | 岩手県(263) | 岩手県(263) | 岩手県(263) | 岩手県(263) | 岩手県(263) |
| 3 | 山形県(168) | 山形県(168) | 山形県(168) | 山形県(168) | 山形県(168) | 山形県(172) |
| 4 | 秋田県(166) | 秋田県(166) | 秋田県(166) | 秋田県(166) | 秋田県(166) | 秋田県(171) |
| 5 | 福島県(153) | 福島県(153) | 福島県(153) | 福島県(153) | 福島県(153) | 福島県(160) |
| 6 | 宮崎県(152) | 宮崎県(152) | 宮崎県(152) | 宮崎県(152) | 宮崎県(152) | 岐阜県(155) |
| 7 | 青森県(138) | 青森県(138) | 青森県(138) | 青森県(138) | 青森県(138) | 広島県(154) |
| 8 | 高知県(134) | 高知県(134) | 高知県(134) | 高知県(134) | 高知県(134) | 島根県(152) |
| 9 | 栃木県(131) | 栃木県(131) | 栃木県(131) | 栃木県(131) | 栃木県(131) | 宮崎県(152) |
| 10 | 福井県(120) | 福井県(120) | 福井県(120) | 福井県(120) | 岐阜県(128) | 高知県(148) |
| 11 | 島根県(114) | 島根県(114) | 島根県(114) | 島根県(114) | 福井県(123) | 青森県(140) |
| 12 | 山口県(109) | 山口県(109) | 山口県(109) | 岐阜県(113) | 広島県(115) | 愛媛県(132) |
| 13 | 長野県(105) | 長野県(105) | 広島県(107) | 山口県(109) | 島根県(114) | 栃木県(131) |
| 14 | 京都府(105) | 京都府(105) | 長野県(107) | 広島県(107) | 山口県(109) | 鳥取県(125) |
| 15 | 岐阜県(103) | 岐阜県(103) | 岐阜県(106) | 長野県(107) | 新潟県(108) | 福井県(123) |
| 16 | 石川県(102) | 石川県(102) | 京都府(105) | 京都府(105) | 石川県(107) | 山口県(120) |
| 17 | 大分県(100) | 大分県(100) | 石川県(102) | 石川県(102) | 長野県(107) | 新潟県(119) |
| 18 | 静岡県(99) | 静岡県(99) | 静岡県(100) | 静岡県(100) | 京都府(105) | 京都府(118) |
| 19 | 広島県(99) | 広島県(99) | 大分県(100) | 大分県(100) | 静岡県(100) | 石川県(116) |
| 20 | 新潟県(98) | 新潟県(99) | 宮城県(99) | 宮城県(99) | 大分県(100) | 山梨県(111) |
このように表にしてみると、北海道の広さがあらためて判る。212市町村という数字が異常に大きく感じたが、北海道の広さからすると、まだまだ少ない方なのだ。ダントツ1位である。全国平均は114平方キロであるが、北海道を除くと88平方キロになる。
我が岐阜県はと言うと、第15位から第6位まで大躍進である。
しかし、この集計方法にも問題があり、結局は面積の広い県が上位に来ているだけである。面積を多い順に並べると、北海道、岩手県、福島県、長野県、秋田県、新潟県、岐阜県、青森県、鹿児島県、広島県、兵庫県、山形県、静岡県、高知県、岡山県、熊本県、宮城県、島根県、宮崎県、栃木県 となっており、上位20道府県のうち15道府県が登場している(青字で示した)。福井県、山口県、京都府、石川県、大分県、の5つが面積が広くないのに、1市町村当たりの面積が広い県というわけだ。
さて、この方法でもさらに問題がある。岐阜県のように2000メートル超級の山を抱える県と、平野部の多い関東地区の県、最高でも300メートルの山しか無い千葉県などと、単純に面積だけで比較するのは問題である。総務省統計局には、こんなときのために(?)、山間部を除いた面積のデータも用意されている。また、よほどの理由が無い限り、国定公園内に住む人もいないだろうから、民有地(宅地、田、畑の合計、山林を除く)の面積から比率を計算してみるか。(こんな統計に意味が無い、と言わないで。しょせん、お遊びですから)
時間が来たので、今回はここまで。
最後におまけとして、岐阜県の変遷、今後の動向を図示してみる。
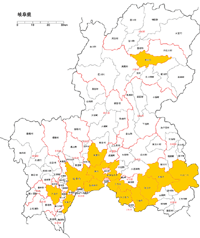 |
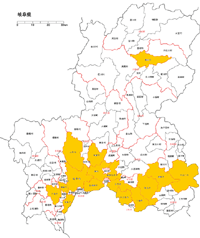 |
 |
| 平成の大合併以前〜2003.4.1
|
2003.5.1 山県市、瑞穂市誕生
|
2004.2.1 飛騨市、本巣市誕生
|
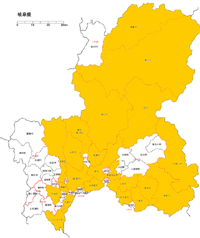 |
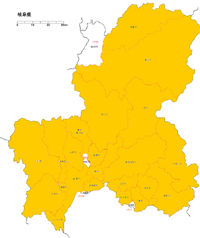 |
黄色で示した部分が「市」
白抜きが郡部 |
| 2005.2.1 郡上市、下呂市誕生、関市拡張
|
2005.3.31 東濃地方再編、大垣市拡張
ひらなみ市誕生、岐阜市拡張、揖斐地方合併その他 |