
 124
124

 124
124
異常な盛り上がりを見せた「豊川」の話題であるが、ちょっといろいろ追記したいことがあり、字数も多くなったので、あえて別番号で書くことにした。一応は、それなりに調べた上での事実を中心にしているが、やはり人の子、どうしても感情論が入ってきてしまう。その点に関しては、当事者方の意見もあるだろうし、その点のお叱りは素直に受ける構えである。さまざまな反論をお受けいたします。
まず、東三河の話題に、時々「大垣」を例に出していたのだが、それに関しての説明をさせていただく。(誰も食いついて来なかったので説明する必要もないのかもしれないが)
何故、大垣の話をさんざん書いてしまったかというと、実は、東三河地区に関しては、私はさほど接点が無く、良く知るわけではない。愛知県に8年間お世話になったとは言え、尾張地区の名古屋にいただけだ。仕事・遊びの関係で、しょっちゅう豊川あたりまでは行っているが、通過するだけの対象であり、住んでいたわけではない。それでも、やはり懐かしい存在ではあるので、それなりに現状を調べたりしていた。知れば知るほど、私の出身地である大垣に似た部分を持つ街である気がしてくる。良く知らない豊川ではあるが、それなりに知る大垣に置き換えて考えていると、(少なくとも私にとっては)非常に理解しやすい。ということである。
そりゃ、東三河地区の人が東三河地区の話題について論議されているところで、いきなり「大垣」が出てきても、唖然としますよね。ふつう。
実は、勘違いしていたのだが、豊川市は、一部、豊橋市と接している。これは大垣市と異なる。大垣は、つい最近の合併で「瑞穂市」が誕生するまで、隣接するのは全て郡部、という非常に珍しい都市であった。全国レベルで探しても、こんな市はほとんど存在しない。人口10万人以上の都市で、一箇所も他の市と接していない都市は、以下の15市だけである。
北海道:北見市 112,040人
北海道:帯広市 173,030人
北海道:函館市 287,637人 ○
北海道:釧路市 191,739人 ○ (訂正:2004.03.16)
青森県:弘前市 177,086人
青森県:八戸市 241,920人 ○
宮城県:石巻市 119,818人 ○
秋田県:秋田市 317,625人 ○
長野県:飯田市 107,381人
三重県:松阪市 123,727人 ○
滋賀県:彦根市 107,860人 ○(琵琶湖)
鳥取県:鳥取市 150,439人 ○
佐賀県:佐賀市 167,955人 ○
熊本県:八代市 106,141人 ○
宮崎県:延岡市 124,761人 ○
※注
・長野県上田市は、ほんのわずかだが千曲市に接している
・鹿児島市は、意外に知られていないが桜島の裏側が鹿児島市であり、垂水市に接している
※訂正
・釧路市を忘れていました、すみません。ご連絡ありがとうございます。
後ろに○印を付けた市は、海に面しており、厳密に言って四方を郡部に囲まれているわけではない。すると、残されたのは、北見、帯広、弘前、飯田、の4市だけとなる。ここに以前は大垣市が含まれて5市であった。それほど、周辺に市部が無く10万以上の都市というのは珍しい存在なのである。
だが、上で述べたように、私の勘違いで、豊川市は、豊橋市と接していた。まあ、大垣市も瑞穂市と接してしまったから似たものとしよう。(全然規模が違うが)
ざっと2都市の概要を比較してみよう。
| 豊川市 | 大垣市 | |
| 単独人口(2000年国勢調査) | 117,327人 | 150,246人 |
| 大合併成功時の人口 | 176,698人 | 301,917人 |
| 対象市町村 | 宝飯郡音羽町
宝飯郡一宮町 宝飯郡小坂井町 宝飯郡御津町 |
養老郡養老町
養老郡上石津町 不破郡垂井町 不破郡関ヶ原町 安八郡神戸町 安八郡輪之内町 安八郡安八町 安八郡墨俣町 揖斐郡池田町 |
| 市の変遷 | 10ヶ村を合併し宝飯郡豊川村
麻生田村、睦美村を合併し豊川町 豊橋市院之子町、牛久保町、八幡村、国府町を合併し、豊川市 八名郡三上村を合併 御油村を合併 現在に至る (三上村を除き、すべて宝飯郡)
|
14ヶ村を合併し安八郡大垣町
安八郡南杭瀬村を合併 安八郡多芸島村を合併 安八郡安井村を合併 不破郡宇留生村、静里村を合併 不破郡綾里村・安八郡洲本村を合併 安八郡浅草村を合併 安八郡川並村、牧村の一部(馬瀬)を合併 安八郡中川村を合併 安八郡和合村を合併 安八郡三城村を合併 不破郡荒崎村分村を合併 不破郡赤坂町を合併 現在に至る |
| 最も近い都市 | 豊橋市 364,856人 | 岐阜市 402,751人 |
| 市名の由来? | 豊川(河川名) 豊川稲荷・・・かな? | 大垣藩 |
無理やり似ているように抽出した、と言われてしまえば元も子もないが、そこそこの人口を持つ工業都市で、歴史があり、周辺が農村部、合併により倍近い規模になろうとしている、と言う点においては、まあ似た境遇といえよう。
ところが決定的に違う点は、ほんの一部を除いて、豊川市は宝飯郡の集合により形成されており、今後予定していた合併も、すべて宝飯郡の範囲であるのに対し、大垣市は、その成り立ちから2つの郡によって構成され、今後合併予定は、さらに養老郡、揖斐郡の一部を含み、4郡にも及ぶ。
さらに、もうひとつ大きな違いを挙げるとすると、「大垣」は元々が藩の名前であり、地名ではない。従って、大垣市内に「大垣」という地名は無い。対して豊川は、JR豊川駅前に、「豊川町」という地名がある。(当初、旧豊川村の名残かと思ったのだが、現在の豊川町は、旧豊川村の中心地とは離れた場所であった。豊川市ができてから町名変更で生まれた町名かもしれない。それでは本来の豊川村はと言うと、現市役所の辺りのようである)
これのどこが重要な話かと言うと、大垣市が合併して新市名を名乗るようになると、「大垣」という地名が地図から永遠に消えてしまうのである。お叱りを覚悟で、あえて新市名を大垣が「西濃市」、豊川が「東三河市」になったとする。すると、「東三河市豊川町」は存在しても、「西濃市大垣町」は存在しない。(無論、上の調査で判明したように「豊川町」自体が、本当の意味の豊川では無さそうなので、本来の豊川という地名は消えてしまっているのかもしれないが)
また、大垣の場合、本来、安八郡だったのだが、合併により安八郡は消滅、それどころか周辺の養老郡、不破郡がいずれも消滅することになる。すると、「西濃市養老町」は残るため、かろうじて「養老」の名が残るが、不破郡不破町というのは無いので、「西濃市不破町」は無い。「不破の関」の「不破」は、地名として残らないことになる。揖斐の名前は、揖斐郡の中心である揖斐町が別のグループで合併を模索中であり、おそらく「揖斐市」が誕生するであろうから、揖斐の名は残りそうだ。すると、大垣、不破、の名前が地図から消滅することになってしまう。
(幸いなことに、周辺町の了承を得て、「大垣市」になることが決定したようだから、「不破」の地名だけが犠牲となってしまっている)
これが「東三河市」にいたっては、もともと三上村以外はすべて宝飯郡だと言うのに、「宝飯」の地名はきれいに消えてしまう。(無論、現実には住民アンケートの結果、合併は白紙撤回、宝飯郡は生き残ったのだが…)
と言うのが、私が「宝飯市」を勧める理由である。
ちなみに、豊川市を構成する全ての村の名前が発見したので、表にまとめてみる。これらの名前は、大部分が現在の地名として生き残っている。
| 江戸期村名 | 明治6年 | 明治8年 | 明治11年 | 明治16年 | 明治22年 | 明治24年 | 明治25年 | 明治26年 | 明治27年 | 明治39年 | 昭和8年 | 昭和18年 | 昭和30年 | 昭和34年 |
| 犬之子村
(院之子村) |
→ | → | → | → | → | → | → | → | → | 豊橋市 | 豊川町 | 豊川市 | → | → |
| 豊川村 | → | → | → | → | 豊川村 | → | → | 豊川町 | → | 豊川町 | ||||
| 北金屋村 | → | → | → | → | ||||||||||
| 古宿村 | → | → | → | → | ||||||||||
| 馬場村 | → | → | → | → | ||||||||||
| 長草村 | → | → | → | → | ||||||||||
| 大崎村 | → | → | → | → | ||||||||||
| 六角村 | → | → | → | → | ||||||||||
| 三蔵子村 | → | → | → | → | ||||||||||
| 本野村 | → | → | → | → | ||||||||||
| 樽井村 | → | → | → | → | ||||||||||
| 谷川村 | → | → | → | → | 麻生田 | → | → | → | → | |||||
| 麻生田村 | → | → | → | → | ||||||||||
| 楠木村 | → | → | 二葉村 | → | ||||||||||
| 楽筒村 | → | → | ||||||||||||
| 向河原村 | → | → | → | → | ||||||||||
| 牧野村 | → | → | → | → | 睦美村 | → | → | → | → | |||||
| 当古村 | → | → | → | → | ||||||||||
| 石原村 | 三谷原村 | → | → | → | ||||||||||
| 雨谷村 | ||||||||||||||
| 三橋村 | ||||||||||||||
| 土筒村 | → | → | → | → | ||||||||||
| 瀬木村 | → | → | → | → | 牛久保町 | → | ||||||||
| 南金屋村 | → | → | → | 中條村 | 牛久保村 | 牛久保町 | → | → | → | |||||
| 鍛冶村 | → | → | → | |||||||||||
| 長山村 | → | 下長山村 | → | → | ||||||||||
| 牛久保村 | → | → | → | → | ||||||||||
| 正岡村 | → | → | → | → | ||||||||||
| 西島村 | → | → | → | → | ||||||||||
| 柑子村 | → | → | → | → | 明子村 | → | → | → | → | |||||
| 行明村 | → | → | → | → | ||||||||||
| 国府村 | → | → | → | → | 国府村 | → | → | → | 国府町 | 国府町 | → | |||
| 為当村 | → | → | → | → | ||||||||||
| 森村 | → | → | → | → | ||||||||||
| 小田淵村 | → | → | → | → | 小田淵村 | → | → | → | → | |||||
| 白鳥村 | → | → | → | → | ||||||||||
| 久保村 | → | → | → | → | ||||||||||
| 市田村 | → | → | → | → | 穂原村 | → | → | → | → | 八幡村 | → | |||
| 野口村 | → | → | → | → | ||||||||||
| 上千両村 | → | → | 千両村 | → | ||||||||||
| 下千両村 | → | → | ||||||||||||
| 八幡村 | → | → | → | → | 平幡村 | → | → | → | → | |||||
| 財賀村 | → | → | → | → | ||||||||||
| 平尾村 | → | → | → | → | ||||||||||
| 三渡野村 | → | → | 三上村 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ||
| 儘ノ上村 | → | → | ||||||||||||
| 古川新田 | → | → | ||||||||||||
| 御油駅 | 御油村 | → | → | → | → | → | 御油町 | → | → | → | → | → | → |
三橋、雨谷、石原が合併して三谷原村、行明、柑子が合併して明子村、平尾、財賀、八幡が合併して平幡村(財賀はどこへ?)、三渡野、儘ノ上、古川新田が合併して三上村、など、あまり由緒ありそうでない名前も出てくるが、それなりに工夫の後が見られる。平幡は評判が悪かったのか、その後再び穂原村との合併時に八幡村に変更している。
名前とは関係ないが、この表を作成していて気づいたのは、御油村の方が、豊川村よりも先に町に昇格している。その御油よりも先に牛久保が町に昇格している。いずれも後に豊川に吸収される形で合併している。さぞや悔しい思いをしたことだろう。特に御油は、単独で(どことも合併することなく)町に昇格するだけの機能、人口を有する村だったと思われる。他の村は、すべて合併によって町に昇格しているのにである。
さて、この表を作成して、何をしようかというと、これらの村の名前が、どれほど現代まで引き継がれているか、を確認しようと思ったのである。早速、2万5000分の1の地図を引っ張り出して、すべての豊川町の町名との比較を行ってみた。下の地図は明治の中頃の「村」ごとに色分けしている。
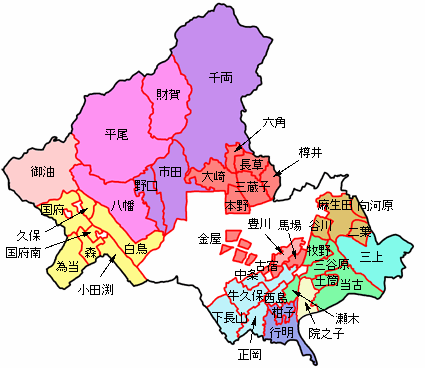
見事に名前が残っていることが判るだろう。赤の領域で「金屋」の集合があるのは、本来の村名では「北金屋村」に相当する場所と思われるのだが、「北金屋町」は存在せず、「金屋町」、「金屋本町」、「金屋元町」、「金屋西町」、「金屋橋町」の5つが点在している。これを北金屋とみなすと、明治中期の地名は、すべて残っていることが判った。白抜きの部分は、新しく生まれた地名であるが、中央部に多い。江戸期の資料によると、本野村と北金屋村にはさまれた領域が豊川村のようだから、現在の市役所のある辺りが、本来の豊川村の中心地のようである。その後、赤の部分が合併して大きな豊川村となった(明治22年)後、鉄道(飯田線※)が村のはずれに開通したために、上の地図の豊川町の辺りに駅ができた。そして、この駅前に「豊川町」として名前が残っている。白の領域は、おそらく初期の段階で合併した豊川村であり、現在の繁華街であるから、いろいろな地名に化けてしまい、初期の名前が残っていないのであろう。
ここまで調べて、一体何を訴えたかったかと言うと、地名とは歴史である。そう簡単に消滅させてしまって良いものではない。三つの村の合併でできた三谷原も、苦渋の選択の結果かもしれない。経費節約のための市町村合併は結構であるが、安易な気持ちで名前を選ぶと、歴史ある名前が消えてしまうことになる。その土地の歴史を消してしまうことにもなる。
ひらがな名前、カタカナ名前など、流行かもしれないが、あまり安易に「かほく市」だとか「東かがわ市」だとか「南アルプス市」だとか命名して欲しくない。
隣の岐阜県では、昨年、市町村合併により「山県郡」が消滅した。しかし、歴史ある山県の名を残そうと「山県市」が誕生し、今後も次々と郡が消滅して行くことになるが、できるだけ地名は残して欲しいと考えるものである。
まあ、その消えゆく名称も、また消してしまう判断もまた、その土地の歴史として刻まれるのだろうが。