
 93
93

 93
93
「一里塚とは」についての記述についても、もっと集計してみたのだが、あまり面白くない結果だったので、公開を止めて、次に詳細固有情報についてまとめてみる。
■大きさ
塚の大きさに関して記述があるのは、63個中、17個であった。ただ、一般的な話の場合と、固有の大きさを示しているのと混在しているので正確では無いが、「五間四方」としているのが、7個であり、一般的な大きさだと思われる。
その他の表現としては、大平一里塚の「底部の縦七・三メートル、横八・五メートルの菱形」というものもある。
大きなものでは、来迎寺のは「半径約11メートル」、豊橋一里山一里塚は「東西十一米、南北十四米」上青島一里塚の「円形百二十平米」、これは、直径12.4mになる。伊達方一里塚は、さらに大きく「直径7間」つまり12.6mである。
高さは1.8mから3.0mが多いが、伊達方だけは「3間」となっている。5.4mということになるから、かなり巨大である。表記上は、直径12.6m高さ5.4mの伊達方が最大である。
あと、間違っていると思われるのが、土山と市場一里塚。全く同じ文面なので、同一人物のミスだろうが、「およそ高さ二・五m円周十二mの大きさ」と記述してある。円周12mということは、直径3.8mになってしまう。直径3.8mに2.5mの土を盛ることは不可能では無いが、かなり困難だと思うのだが。おそらく直径12mの間違いであろう。
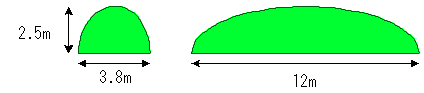
あとは、塚の規模不明、とわざわざ書かれているのが1個あった。
■日本橋からの里数
江戸日本橋から何里か、という情報も結構多くの説明文で見かけるが、実際に確認できたのは、39塚だけである。この情報に関しては、単なる碑のみにも書かれていることが多いので、説明文なしの一里塚からも採取してみた。すると6塚が追加され、全部で45塚であった。
最遠は笠寺一里塚の88里目の記述であり、その先は確認されていない。七里の渡しを渡ると、もはや日本橋からの里数というのに意味が無いのかもしれない。何個目か、という数え方は出来るが、それでも反論はあるだろうし。しかし大概帳などで、宿場間の里数が正式に書かれているのだから、一里塚の里数も、正式な番号というのがあっても不思議では無いのだが。
七里の渡し後に、かろうじて確認できるのは、中富田一里塚の表記で、「江戸へおよそ百里(約400キロ)」という記述だけである。ちなみに私の調査による里数では、中富田の一里塚は、103番目の一里塚である。およそ百里、という表現に苦悩の痕が見える。
都道府県別に分類してみる。
| 都道府県 |
塚数
|
里数あり
|
(碑のみ)
|
里数記述比率
|
| 東京都 |
4
|
1
|
0
|
|
| 神奈川県 |
20
|
16
|
1
|
|
| 静岡県 |
42
|
21
|
2
|
|
| 愛知県 |
19
|
6
|
5
|
|
| 三重県 |
12
|
1
|
0
|
|
| 滋賀県 |
15
|
0
|
0
|
|
| 京都府 |
1
|
0
|
0
|
|
| 合計 |
113
|
45
|
8
|
碑のみの一里塚であるが、葛川一里塚の記述には、「江戸より56里、京より69里」となっている。この記述は、日本橋―京間が125里であることを示している。125という数値は、宿場間を合計した距離から計算したようである。